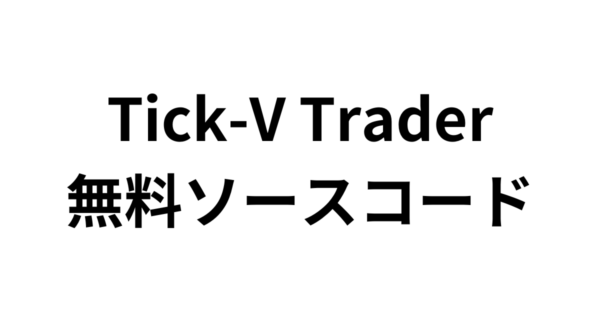この記事ではJupyter Notebookについて詳しく解説します。
Jupyter Notebookとは?
Jupyter Notebook(ジュピター・ノートブック)は、プログラムコード、その実行結果、説明文、数式、画像、グラフなどを一つにまとめて記録・共有できる、Webブラウザ上で動作する対話型の開発環境です。
一言で言うと、「実行できるデジタルな実験ノート」のようなものです。特に、データ分析や機械学習、科学技術計算の分野で絶大な人気を誇っています。
なぜ人気があるの? 主な特徴
Jupyter Notebookが広く使われているのには、いくつかの理由があります。
- 対話的な実行(Interactive Execution)
- プログラムを「セル」と呼ばれる小さな単位に分割し、一つずつ実行できます。
- これにより、試行錯誤しながらコードを書き進めることが非常に簡単になります。「この処理の結果はどうなるかな?」というのを、その場で確認しながら分析を進められるのが最大の利点です。
- コードと説明文、可視化の融合
- コード(Codeセル)だけでなく、Markdown形式で説明文や見出しを書けるセル(Markdownセル)があります。
- MatplotlibやSeabornといったライブラリを使えば、グラフやプロットをノートブック内に直接表示できます。
- これにより、「何のためにこのコードを実行したのか」という思考の過程と、「その結果どうなったのか」というアウトプットをセットで記録できます。
- 共有と再現性の高さ
- ノートブックは
.ipynbというファイル形式で保存されます。このファイルにはコード、実行結果、説明文がすべて含まれています。 - このファイルを他人に渡すだけで、実行環境さえあれば誰でも同じ分析手順と結果を再現できます。研究やチームでの共同作業に非常に便利です。
- ノートブックは
- 多言語対応(Polyglot)
- もともとはPython向けに開発されましたが、「カーネル」と呼ばれる実行エンジンを切り替えることで、R、Julia、Scalaなど、様々なプログラミング言語で利用できます。
- 豊富なエコシステム
- Pandas(データ操作)、NumPy(数値計算)、Matplotlib(グラフ描画)、Scikit-learn(機械学習)といった、データサイエンスに必須のライブラリとの相性が抜群です。
基本的な構成要素
Jupyter Notebookを理解するために、2つの重要な概念を覚えましょう。
- セル (Cell)
ノートブックを構成する最小単位です。主に2種類あります。- コードセル (Code Cell): プログラムコードを記述し、実行するためのセル。実行すると、セルの直下に出力が表示されます。
- Markdownセル (Markdown Cell): テキスト、見出し、箇条書き、数式、画像の埋め込みなど、説明文を記述するためのセル。
- カーネル (Kernel)
実際にコードを実行する「エンジン」の部分です。ユーザーがコードセルで実行命令を出すと、カーネルがそのコードを解釈して計算を行い、結果をノートブックに返します。カーネルは裏側で動いており、変数の状態などを保持しています。- もしプログラムが無限ループに陥ったり、動作がおかしくなったりした場合は、「Kernel」メニューから「Restart」を選ぶことで、カーネルを初期状態に戻せます。
始め方(インストールと起動)
Jupyter Notebookを始める最も簡単な方法は、Anaconda(アナコンダ)をインストールすることです。
- Anacondaのインストール
- Anacondaの公式サイトから、お使いのOS(Windows, macOS, Linux)に合ったインストーラーをダウンロードしてインストールします。
- Anacondaには、Python本体、Jupyter Notebook、そしてデータ分析でよく使われるライブラリ(Pandas, NumPyなど)がすべて含まれているため、これだけで準備完了です。
- Jupyter Notebookの起動
- Windowsの場合: スタートメニューから「Anaconda Prompt」を起動し、以下のコマンドを入力してEnterキーを押します。
- macOSの場合: 「ターミナル」アプリを起動し、以下のコマンドを入力してEnterキーを押します。
jupyter notebookすると、自動的にWebブラウザが立ち上がり、Jupyterのホーム画面が表示されます。
簡単な使い方
- ホーム画面の右上にある「New」ボタンをクリックし、「Python 3」などを選択すると、新しいノートブックが作成されます。
- 最初のセル(コードセル)に、簡単なPythonコードを入力してみましょう。
print("Hello, Jupyter!") - コードを入力したら、
Shift + Enterキーを押します。すると、コードが実行され、セルの下にHello, Jupyter!と表示されます。 - 次に、グラフを描画してみましょう。新しいセルに以下のコードを入力して
Shift + Enterを押します。import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np x = np.linspace(0, 10, 100) y = np.sin(x) plt.plot(x, y) plt.title("Sine Curve") plt.xlabel("x") plt.ylabel("sin(x)") plt.grid(True) plt.show()セルの下にサインカーブのグラフが直接表示されるはずです。
豆知識:JupyterLabとの違い
最近では、Jupyter Notebookの次世代版としてJupyterLab(ジュピター・ラボ)も広く使われています。
- Jupyter Notebook: 1つのノートブックを1つのタブで開く、シンプルで伝統的なインターフェース。
- JupyterLab: タブ形式で複数のノートブックやターミナル、テキストエディタを並べて表示できる、より高機能でIDE(統合開発環境)に近いインターフェース。
これから始めるのであれば、よりモダンなJupyterLabから使い始めることをお勧めします。起動コマンドは jupyter lab です。
便利なショートカットキー
Jupyterを快適に使うには、ショートカットキーが必須です。
| キー | コマンドモードでの動作 (セルを選択しているが、入力モードではない状態) |
|---|---|
Shift + Enter | セルを実行し、下のセルへ移動(最もよく使う) |
Ctrl + Enter | セルを実行し、その場に留まる |
A | 選択中のセルの上 (Above) にセルを挿入 |
B | 選択中のセルの下 (Below) にセルを挿入 |
D, D (Dを2回) | 選択中のセルを削除 |
M | 選択中のセルをMarkdownセルに切り替える |
Y | 選択中のセルをコードセルに切り替える |
Z | セルの削除を取り消す (Undo) |
まとめ
Jupyter Notebookは、試行錯誤しながらデータと対話し、その過程と結果を美しく記録するための強力なツールです。特にデータサイエンスを学ぶ上では、避けては通れない必須の環境と言えるでしょう。ぜひインストールして、その便利さを体験してみてください。
Jupyter NotebookをFX取引に活用するには?
FX取引にJupyter Notebookを活用する方法を、具体的なステップとコード例を交えて解説します。
Jupyter Notebookでできること(FX取引の文脈で)
Jupyter Notebookは、主に**「取引戦略をデータに基づいて構築し、検証するための研究室」**として機能します。具体的には以下のようなことが可能です。
- ヒストリカルデータの取得と整形
- データの可視化と分析(チャート、移動平均線など)
- テクニカル指標の計算(RSI, MACD, ボリンジャーバンドなど)
- 取引戦略のプロトタイピングとバックテスト
- 機械学習を用いた価格予測モデルの構築
- 取引結果の分析とパフォーマンス評価
- ブローカーAPIと連携した自動発注(上級者向け)
具体的な活用ステップとコード例
ここでは、最も基本的な**「移動平均線ゴールデンクロス戦略」**を例に、Jupyter Notebookでの分析フローを見ていきましょう。
前提:必要なライブラリのインストール
まず、データ分析に必要なライブラリをインストールします。ターミナルやAnaconda Promptで以下のコマンドを実行してください。
pip install numpy pandas matplotlib mplfinance pandas-ta- pandas: データ操作の主役
- matplotlib: グラフ描画
- mplfinance: 金融チャート(ローソク足)の描画に特化
- pandas-ta: テクニカル指標を簡単に計算できるライブラリ
ステップ1:ヒストリカルデータの取得
まず、FXのヒストリカルデータ(ここではUSD/JPYの1時間足)を用意します。多くのFXブローカーがCSV形式でデータを提供しています。ここでは、サンプルとしてデータを作成しますが、実際にはご自身で用意したCSVファイルを読み込みます。
# --- Jupyter Notebookのセルに入力 ---
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import mplfinance as mpf
import pandas_ta as ta
# 実際の取引では、FXブローカーからダウンロードしたCSVを読み込む
# 例: df = pd.read_csv('USDJPY_1H.csv', index_col='Date', parse_dates=True)
# ここではサンプルのダミーデータを作成
dates = pd.date_range(start='2023-01-01', periods=500, freq='H')
price = 130 + np.random.randn(500).cumsum() * 0.1
high = price + np.random.uniform(0, 0.1, 500)
low = price - np.random.uniform(0, 0.1, 500)
close = price + np.random.uniform(-0.05, 0.05, 500)
open_ = close.shift(1)
open_[0] = 130
df = pd.DataFrame({
'Open': open_,
'High': high,
'Low': low,
'Close': close
}, index=dates)
df.head()実行結果(例):
ステップ2:テクニカル指標の計算
短期(25期間)と長期(75期間)の単純移動平均線(SMA)を計算します。pandas-taを使えば非常に簡単です。
# --- 新しいセルに入力 ---
# 短期と長期の移動平均線を計算
df.ta.sma(length=25, append=True) # 'SMA_25'という列が追加される
df.ta.sma(length=75, append=True) # 'SMA_75'という列が追加される
# 不要な列を削除し、欠損値のある行を削除
df = df.dropna()
df.tail()実行結果(例):
ステップ3:データの可視化
計算した移動平均線とローソク足チャートを重ねてプロットします。これで、視覚的にゴールデンクロス(短期線が長期線を上抜く)やデッドクロス(下抜く)を確認できます。Generated python
# --- 新しいセルに入力 ---
# mplfinanceを使ってローソク足チャートと移動平均線を描画
# 直近200期間分を描画
plot_df = df.tail(200)
# 描画する追加プロットを定義
add_plots = [
mpf.make_addplot(plot_df['SMA_25'], color='blue', width=0.7),
mpf.make_addplot(plot_df['SMA_75'], color='red', width=0.7),
]
mpf.plot(plot_df, type='candle', style='yahoo',
title='USD/JPY 1H Chart with SMA',
ylabel='Price (JPY)',
addplot=add_plots,
figsize=(15, 7))実行結果:
Jupyter Notebookなら、このようにコードを実行した直下にグラフが表示されるため、分析が非常にスムーズです。
ステップ4:取引シグナルの生成とバックテスト
ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売るという戦略のシグナルを生成し、簡単なバックテストを行います。
# --- 新しいセルに入力 ---
# シグナルの生成
# 短期SMA > 長期SMA なら 1 (買いシグナル), そうでなければ 0
df['Signal'] = np.where(df['SMA_25'] > df['SMA_75'], 1, 0)
# ポジションの変化点を特定(ドテン売買)
# シグナルが変化した点(例: 0→1, 1→0)が取引のタイミング
df['Position'] = df['Signal'].diff()
# --- バックテスト結果を可視化 ---
plt.figure(figsize=(15, 7))
plt.plot(df.index, df['Close'], label='Close Price')
plt.plot(df.index, df['SMA_25'], label='SMA 25', color='blue', linestyle='--')
plt.plot(df.index, df['SMA_75'], label='SMA 75', color='red', linestyle='--')
# 買いシグナル(ゴールデンクロス)の点をプロット
plt.plot(df[df['Position'] == 1].index,
df['SMA_25'][df['Position'] == 1],
'^', markersize=10, color='g', label='Buy Signal')
# 売りシグナル(デッドクロス)の点をプロット
plt.plot(df[df['Position'] == -1].index,
df['SMA_25'][df['Position'] == -1],
'v', markersize=10, color='r', label='Sell Signal')
plt.title('USD/JPY - SMA Crossover Strategy')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()実行結果:
ステップ5:パフォーマンスの評価
最後に、この戦略がどれくらいの利益を生んだかを簡単に計算します。Generated python
# --- 新しいセルに入力 ---
# 1期間ごとのリターンを計算
df['Returns'] = np.log(df['Close'] / df['Close'].shift(1))
# 戦略のリターンを計算(シグナルが出た次の日からポジションを持つと仮定)
df['Strategy_Returns'] = df['Returns'] * df['Signal'].shift(1)
# 累積リターンを計算
df['Cumulative_Returns'] = (1 + df['Returns']).cumprod()
df['Cumulative_Strategy_Returns'] = (1 + df['Strategy_Returns']).cumprod()
# 結果をプロット
plt.figure(figsize=(15, 7))
plt.plot(df.index, df['Cumulative_Returns'], label='Buy and Hold')
plt.plot(df.index, df['Cumulative_Strategy_Returns'], label='SMA Crossover Strategy')
plt.title('Strategy Performance')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()実行結果:
このグラフで、青線(単純保有)とオレンジ線(戦略)を比較し、戦略の有効性を評価します。
Jupyter Notebook活用のメリットまとめ
- 対話的な分析: コードを少し書き、実行し、結果を見て、また修正…というサイクルを高速に回せる。
- 思考プロセスの記録: コード、グラフ、説明文を一つのファイルに残せるため、「なぜこの戦略を試したのか」という経緯を後から追いやすい。
- 豊富なライブラリ: Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlowなど、データ分析から機械学習まで、あらゆるツールが揃っている。
- 再現性: ノートブックを共有すれば、誰でも同じ分析を再現できる。
注意点
- Jupyterは分析・開発環境: リアルタイムの高速取引(HFT)には向きません。あくまで戦略を練り、検証する場です。
- バックテストの罠: スプレッド、手数料、スリッページなどを考慮しない単純なバックテストは、過度に良い結果が出がちです。より本格的なバックテストにはbacktesting.pyやZiplineといった専門ライブラリの利用を検討しましょう。
- 過学習(カーブフィッティング): 過去のデータに過剰に適合した戦略は、未来の相場では機能しない可能性があります。
Jupyter Notebookを使いこなせば、感覚的な取引から脱却し、データに基づいた客観的な取引戦略を構築する強力な武器になります。ぜひ試してみてください。
Jupyter NotebookとGoogle Colabの違いは?
この2つは非常によく似ていますが、**「どこで実行するか」「誰が環境を管理するか」**という点で大きな違いがあります。
一言でいうと
- Jupyter Notebook: **自分のPC(ローカル環境)**で動かす、伝統的で自由度の高いツール。
- Google Colab: Googleのクラウド上で動かす、環境構築不要ですぐに使えるJupyter Notebook。
両者の関係は、「Google Colabは、Googleが提供するJupyter Notebookのクラウドサービス版」と理解すると分かりやすいです。
比較表
| 項目 | Jupyter Notebook (ローカル) | Google Colaboratory (Google Colab) |
| 実行場所 | 自分のPC (ローカル) | Googleのクラウドサーバー |
| 環境構築 | 必要 (Anaconda等のインストール) | 不要 (WebブラウザとGoogleアカウントだけ) |
| ハードウェア | 自分のPCのスペック (CPU, メモリ) に依存 | 強力なGPU/TPUを無料で利用可能 |
| 主なライブラリ | 自分でインストールが必要 | 主要なライブラリはプリインストール済み |
| ファイル管理 | ローカルのファイルシステム | Google Drive との連携が基本 |
| 共有機能 | ファイル(.ipynb)を手動で送受信 | URLを共有するだけで共同編集が可能 |
| 実行時間 | 制限なし | 連続実行時間に制限あり (無料版は約12時間でリセット) |
| 費用 | 無料 (PCの電気代のみ) | 基本無料 (有料版のColab Pro/Pro+あり) |
| オフライン利用 | 可能 | 不可 (インターネット接続が必須) |
| 向いている用途 | ・機密性の高いデータ分析<br>・安定した長時間実行<br>・PC環境の完全なカスタマイズ | ・機械学習、ディープラーニング<br>・環境構築の手間を省きたい初心者<br>・チームでの共同作業<br>・ハイスペックな計算を無料で試したい |
各項目の詳細な解説
1. 実行環境と環境構築
- Jupyter Notebook: 自分のPCにPythonやAnacondaをインストールする必要があります。少し手間はかかりますが、一度構築すれば自分好みに完全にカスタマイズできます。
- Google Colab: 最大のメリットは環境構築が一切不要なことです。WebブラウザでColabのサイトにアクセスし、Googleアカウントでログインするだけで、すぐにPythonコードを書き始められます。
2. ハードウェア(特にGPU/TPU)
- Jupyter Notebook: 自分のPCの性能がそのまま計算能力になります。ディープラーニングなど、GPUを必要とする重い処理を行うには、高価なGPUを搭載したPCが必要です。
- Google Colab: 無料でNVIDIAのGPU(Tesla T4など)やGoogleのTPUを利用できます。これは、特に機械学習を学ぶ学生や研究者にとって非常に大きなアドバンテージです。
- [ランタイム] > [ランタイムのタイプを変更] から簡単に切り替えられます。
3. ファイル管理と共有
- Jupyter Notebook: 作成したファイル (.ipynb) はPCのローカルフォルダに保存されます。共有するには、ファイルをメールに添付したり、GitHubにアップロードしたりする必要があります。
- Google Colab: ファイルは自動的にGoogle Driveに保存されます。Googleドキュメントやスプレッドシートのように、URLを共有するだけで他の人とリアルタイムで共同編集ができます。教育やチームでのコラボレーションに非常に便利です。
4. ライブラリ
- Jupyter Notebook: pip install や conda install を使って、必要なライブラリを自分でインストールします。
- Google Colab: Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorchなど、データサイエンスや機械学習でよく使われる主要なライブラリがあらかじめインストールされています。もし追加で必要なライブラリがあれば、ノートブック上で !pip install … と実行すれば簡単にインストールできます(ただし、セッションが切れると再インストールが必要)。
5. 実行時間の制限
- Jupyter Notebook: 自分のPCで動かすので、PCの電源が入っている限り実行時間に制限はありません。数日かかるような長時間計算も可能です。
- Google Colab: 無料版では、約12時間でランタイム(実行環境)がリセットされます。また、90分間操作がないと自動的にセッションが切断されます。長時間の学習や本番運用には向いていません。有料プランにすると、この制限が緩和されます。
どちらを選ぶべきか?
あなたの目的によって最適な選択は異なります。
🟢 Google Colab を選ぶべき人
- プログラミングやデータ分析の初心者: 環境構築でつまずくことなく、すぐに始めたい人。
- 機械学習・ディープラーニングを学びたい人: 無料で高性能なGPUを使いたい人。
- 学生やチームで共同作業をしたい人: 簡単な共有機能やコメント機能を使いたい人。
- PCのスペックに自信がない人: 重い計算をクラウドに任せたい人。
🔵 Jupyter Notebook (ローカル) を選ぶべき人
- 企業の機密データなど、外部に置けないデータを扱う人: セキュリティが重要な場合。
- オフライン環境で作業する必要がある人: インターネット接続が不安定な場所で作業する場合。
- 実行時間に制限なく、長時間のバッチ処理を行いたい人。
- 特定のライブラリバージョンなど、環境を細かく・永続的にカスタマイズしたい人。
まとめ
**「手軽さとパワフルな計算環境ならGoogle Colab、自由度と安定性ならローカルのJupyter Notebook」**と覚えておくと良いでしょう。
最近では、まずGoogle Colabで手軽に試してみて、本格的に開発する段階になったらローカルのJupyter環境に移行する、という使い分けも一般的です。どちらもJupyter Notebook形式(.ipynb)のファイルは共通して使えるので、両方をうまく活用するのが賢い使い方と言えます。
Jupyter Notebookと価格予想モデルの関係性は?
一言で言うと、Jupyter Notebookは「価格予測モデルを研究・開発するための理想的な実験室」です。
モデル開発者は、Jupyter Notebookという対話的な環境の中で、データを分析し、モデルを構築し、その性能を評価するという一連の作業を行います。
なぜ価格予測モデルの開発にJupyter Notebookが使われるのか?
価格予測モデルの開発は、一度で完璧なものができるわけではなく、何度も試行錯誤を繰り返すプロセスです。Jupyter Notebookの以下の特徴が、このプロセスと完璧にマッチしています。
- 対話的なデータ探索と可視化
- 価格データ(株価、FX、不動産価格など)を読み込み、すぐにグラフで可視化できます。
- 「この期間の価格の動きはどうなっているか?」「他の指標との相関は?」といった疑問を、コードを書いては実行し、その場で結果を確認しながら深掘りできます。
- 試行錯誤のスピード
- モデルの性能は「特徴量(説明変数)」の作り方で大きく変わります。Jupyter Notebookなら、「移動平均線を追加してみよう」「過去3日間の価格を特徴量にしてみよう」といったアイデアをセル単位で素早く試し、結果を比較検討できます。
- モデルのパラメータ(ハイパーパラメータ)を変えて、性能がどう変わるかを何度も実験するのも非常に簡単です。
- 思考プロセスと結果の記録
- コード(何をしたか)、実行結果のグラフや数値(どうなったか)、そしてMarkdownセルによる説明文(なぜそうしたか)を一つのファイルにまとめて残せます。
- これにより、後から自分の分析プロセスを振り返ったり、チームメンバーに「こういう意図でこのモデルを作った」と共有したりするのが非常に容易になります。
Jupyter Notebookを使った価格予測モデル開発の具体的なフロー
一般的な価格予測モデル(例えば、明日の株価を予測するモデル)をJupyter Notebookで開発する流れは、以下のようになります。
Step 1: データの準備と読み込み
まず、過去の価格データをpandasライブラリを使って読み込みます。
# --- Jupyter Notebookのセル ---
import pandas as pd
# 例: 'stock_price.csv'というファイルからデータを読み込む
# Date列をインデックスにし、日付として解釈する
df = pd.read_csv('stock_price.csv', index_col='Date', parse_dates=True)
df.head()Step 2: 探索的データ分析 (EDA) と可視化
データをグラフにして、どのような特性があるかを理解します。Jupyter Notebookなら、コードのすぐ下にグラフが表示されます。
# --- 新しいセル ---
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(15, 7))
plt.plot(df['Close']) # 終値の推移をプロット
plt.title('Stock Price History')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Price')
plt.grid(True)
plt.show()Step 3: 特徴量エンジニアリング (Feature Engineering)
予測に役立ちそうな新しいデータ(特徴量)を作成します。ここがモデルの性能を左右する最も重要なパートであり、Jupyter Notebookでの試行錯誤が活きる場面です。
# --- 新しいセル ---
# 例: 5日移動平均と25日移動平均を特徴量として追加
df['SMA_5'] = df['Close'].rolling(window=5).mean()
# 例: 1日前の終値を特徴量として追加 (ラグ特徴量)
df['Lag_1'] = df['Close'].shift(1)
# 欠損値を含む行を削除
df = df.dropna()
df.head()Step 4: モデルの選択と学習
特徴量(X)と予測したい対象(y、例えば翌日の終値)を定義し、機械学習モデル(scikit-learnなど)に学習させます。
# --- 新しいセル ---
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
# 特徴量(X)とターゲット(y)を定義
# 翌日の終値を予測するため、ターゲットはずらす
X = df[['SMA_5', 'Lag_1']]
y = df['Close'].shift(-1).ffill() # 最後の行はNaNになるので前方で埋める
# データを学習用とテスト用に分割
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, shuffle=False) # 時系列データなのでシャッフルしない
# モデルを定義して学習
model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)Step 5: モデルの評価と可視化
学習済みモデルが未知のデータ(テストデータ)に対してどれくらい正確に予測できるかを評価します。
# --- 新しいセル ---
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# テストデータで予測を実行
predictions = model.predict(X_test)
# 予測結果と実際の値を並べて表示
results = pd.DataFrame({'Actual': y_test, 'Predicted': predictions}, index=y_test.index)
print(results.head())
# RMSE (Root Mean Squared Error)で精度を評価
rmse = mean_squared_error(y_test, predictions, squared=False)
print(f'RMSE: {rmse}')
# 予測結果をグラフで可視化
plt.figure(figsize=(15, 7))
plt.plot(results['Actual'], label='Actual Price')
plt.plot(results['Predicted'], label='Predicted Price', linestyle='--')
plt.legend()
plt.title('Model Prediction vs Actual')
plt.show()このグラフを見ることで、モデルがどの程度価格の動きを追従できているかを直感的に判断できます。
Jupyter Notebookの役割と限界
- 役割: あくまで「研究開発環境」です。アイデアを形にし、データと対話し、最適なモデルを探求するためのサンドボックス(砂場)です。
- 限界: Jupyter Notebookは、リアルタイムで動き続ける取引システムや、本番環境での自動運用には直接は使われません。開発したモデルは、学習済みのファイル(例:
pickleファイル)として保存し、それをPythonスクリプト(.py)から読み込んで本番システムに組み込むのが一般的です。
まとめ
Jupyter Notebookと価格予測モデルは、「実験室と研究対象」のような関係です。Jupyter Notebookが提供する対話的で視覚的な環境があるからこそ、データサイエンティストは複雑な価格データの中からパターンを見つけ出し、試行錯誤を繰り返しながら、より精度の高い予測モデルを効率的に開発することができるのです。